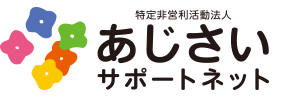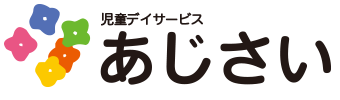一日の様子
未就学児
- 10:00 ~
- 順次来所、入室
手洗い、所持品の片付け、排泄、シール貼り
自由遊び(ブロック、絵本、おままごとなど)
- 10:30 ~
- 朝の会(お返事・インタビュー・絵本読み聞かせ)
- 10:50 ~
- 排泄等
- 11:00 ~
- 戸外遊び(公園遊び・近隣散策など)
- 雨天時は室内遊び。(ボールプール、風船、体操など)
- 月に2度の言語聴覚士による個別言語指導もこの時間帯に行います。
- 12:20 ~
- 昼食準備(手洗い・排泄等)
- 12:20 ~
- おひるごはん(お弁当持参)
- 13:00 ~
- 課題活動、室内遊び
- 製作・感触遊び・ごっこ遊びなど
- お天気が良い日は戸外で遊ぶこともあります。
- お昼寝が必要なお子さんはこの時間にします。
- 14:50 ~
- おやつ準備
- 15:00 ~
- おやつ
- 15:30 ~
- 帰りの会
- 15:30 ~
- 順次お迎え
就学児
- 13:30 ~
- 学校お迎え・保護者送迎児童受入れ
- 14:30 ~
- 順次来所、入室
手洗い、所持品の片付け、排泄、学習準備
- 14:50 ~
- 学習(宿題やあじさいで準備した教材に取り組みます。)
- 15:10 ~
- おやつ
- 15:30 ~
- 今日の予定の確認等
(みんなで集まって挨拶と活動内容の確認等を行います。)
- 15:40 ~
- 戸外遊び(天気の良い日は積極的に戸外で体を動かして遊びます。)
雨天時は室内遊び(創作活動、感触遊び、ごっこ遊び、集団遊びなど)- その日のメンバーや個々の目標に則した活動を設定しています。
- 17:10 ~
- 片付け・帰りの準備
- 17:20 ~
- 帰りの会
- 17:30 ~
- 順次お迎え、送迎。
活動内容
母子分離
お子さまの
ペースで無理なく
行います。
母子分離
お母さんと離れても安心して過ごすことができるように。
あじさいでは、朝、玄関でお母さんと離れ、お友達と一緒に過ごす単独通所となっています。お母さんと離れても安心して過ごすことができるように、場所や周囲の人々、活動の様子に慣れるまで指導員が1対1でかかわります。ひとりひとりが自分のペースで無理なく療育活動に慣れていくことができるような体制を取っています。
※母子分離に不安がある保護者の方に対しては、ご相談に応じています。
遊び を大切に。
夢中で遊ぶことができるように
「やってみたい!」を「できた!」「楽しかった!」に変えながら、
意欲の向上や自信につなげていきます。
遊びには子どもの発達を促すたくさんの要素が盛り込まれています。子どもたちは遊びを通じて成長や発達に必要な多くの経験を積み、力をつけていきます。
例えばおままごとでは、まずどんなことをしたいかをイメージします(想像すること)。次にその為に何が必要かを考えます(考えること)。そして必要なことを要求したり必要なものを自分で探したりします(行動してみること)。遊びを進める中では、どうしたらフライパンの食べ物をお皿に上手に移せるか、お母さんのような仕草になるかなどを考え、試行錯誤して体を動かします(体を動かすこと)。また同じ場に友達がいれば、場や物を共有したりやり取りをしたりする場面もでてきます(人とかかわること)。
子どもたちはそれらひとつひとつを意識しているわけではありません。夢中になって楽しく遊んでいるうちに、発達に必要な経験が自然と積み重なっていくのです。
しかし、発達に心配のあるお子さんは、そのどこかに困難さを抱えていることがあり、遊びを「楽しい」と感じにくいことが多くあります。何をすればよいのかわからない、友達が何をしているのか理解できない、特定の事物にしか興味関心をもてないなどの理由から、遊びに満足感や充実感を得にくく、生活全般に意欲や自信がもてなくなってしまうことにもつながります。
あじさいの療育では、ひとりひとりが充実して遊ぶことができるように、イメージをもちやすい教材をひとりひとりの興味に合わせて手作りしたり選定したりしています。一目見ただけで何をするのかがわかる場づくりや、思わず手に取ってみたくなるような教材で「やってみたい!」という気持ちを育てます。そして「やってみたい!」を「できた!」「楽しかった!」に変えながら、意欲の向上や自信につなげていきます。



お子さまはもちろん
保護者の方への
支援
も行っています。
保護者支援
アドバイザーを迎えての保護者茶話会を開催。
保護者の方々と共にお子さまの成長を支えていきます。
未就学のお子さんについては、保護者の方に送迎を行っていただいております。送り迎えの際にお子さまの様子を詳しくお知らせしたり、不安なことなどがあれば随時面談を行ったりしながら、保護者の方々と共にお子さまの成長を支えていきます。
また、定期的に保護者茶話会を開催しています。市内の保育園で40年間、発達に心配のあるお子さんをはじめ様々なお子さんや親御さんとかかわってきた方をアドバイザーに迎え、親御さんの思いや子育ての悩みや不安をもちよって話したり、就園、就学に向けての情報交換を行ったりしています。
関係機関と
連携
を取り多方面から
支援します。
関係機関との連携
幼稚園、保育園、学校、医療機関、相談室など
関係機関と連絡を取り合いながら多方面から支援します。
幼稚園、保育園、学校、医療機関、相談室など関係機関と連絡を取り合いながらお子さまの育ちを多方面から支援します。就園や就学の際には、ご希望に応じて幼稚園や学校に引継ぎを行い(引継ぎ書の作成、幼稚園や学校の先生と面談しての引継ぎなど)就園後も園を訪問したり担任の先生と連絡を取り合ったりしながら継続的に支援します。
戸外遊び
お天気の良い日はできるだけ毎日戸外で
遊ぶようにしています。



お天気の良い日は、みんなで歩いてお散歩をします。外の空気や自然に触れて心地よさを味わいながら公園で思う存分体を動かしたり季節ならではの遊びを楽しんだりします。
午前中の適度な運動は、食事や睡眠などの生活リズムを整えることにもつながりますので、お天気の良い日はできるだけ毎日戸外で遊ぶようにしています。
また、友達と手をつないで歩く経験を重ねることは、交通ルールを学ぶなど、幼稚園などの集団参加への準備にもつながります。
課題活動への参加
幼稚園や保育園、小学校での生活に必要な力を
身につけます。



幼稚園や保育園への入園を見越して、これから経験すると思われる活動を少しだけ先取りして経験できるようにしています。
初めてのことが苦手なお子さんが多い為、先に経験しておくことで、大きな集団に入った時の不安や負担を少しでも軽減できるようにしていきます。小集団で指導員が個別に丁寧に対応しながら、課題活動(体操、お絵かき、工作など)にじっくりと取り組み、幼稚園や保育園、小学校での生活に必要な力を身につけます。
体操教室
楽しみながら挑戦できる喜びを
皆で分かち合います。



体操経験者による、体操の時間があります。跳び箱、平均台、鉄棒、マットなどを使い、楽しみながら色々なことに挑戦しています。マットは転がるところから、跳び箱は段を1段上るところから、スモールステップで楽しみながら少しずつ技術の向上を目指します。
楽しみながら挑戦し、できなかったことができる喜びを自分自身で感じ、それを周囲のみんなでも喜び合う姿がたくさんみられます。
ムーブメント療法(作業療法士による)
作業療法士の先生が来所。子どもの自発性を
尊重し、音楽に合わせて体を動かします。



1ヶ月に1度、北海道文教大学教授である作業療法士の先生が来所されます。日本ダンスセラピー協会の認定ダンスセラピストでもある先生がムーブメント療法を行います。ムーブメント療法では、子どもの自発性を尊重しながら、音楽に合わせて体を動かしたり色々なポーズを取ったりしながら、子ども自身が動くことや考えること感じることを喜ぶことで調和の取れた発達を目指します。また、指導員もムーブメントについて学び日々の療育に生かしています。
幼稚園・保育園平行通所
幼稚園や保育園などの集団活動の中で自信のなさや苦手さを感じている部分について、補完をしていきます。


幼稚園や保育園に通うお子さまも通所しています。大きな集団の活動の中で自信のなさや苦手さを感じている部分について、小集団で丁寧に支援しながら補完していきます。「ハサミがうまく使えない」「体を動かすことが苦手」「お友達とすぐにトラブルになってしまう」など、手先の不器用さや運動の苦手さ、人とのかかわりの不得手さなど、ひとりひとりがもつ課題に対して、小集団の活動の中で丁寧に指導を行い、幼稚園、保育園での活動、さらには小学校入学に自信をもって臨むことができるように支援しています。
年中、年長さんになると、お友達や年長さんの姿に刺激を受けながら、文字を書く練習や逆上がりなどに自ら挑戦しようとする気持ちをもつお子さんも増えてきます。お「やってみたい!」と感じたことをすぐに実現できるように、そして達成感や満足感を味わえるように支えています。
ことばの発達
言語聴覚士の先生が来所。
お子さまへの個別言語療育を行っています。
1カ月に2回言語聴覚士の先生が来所されます。お子さまへの個別の言語療法及び療育スタッフへのコンサルテーションも行っていただいています。
行事
様々な行事を年間通して行っています。


お誕生会、親子遠足、発表会、修了お祝い会を行っています。